
「水滞」になると、水分ばかりか、からだの各器官に行き渡るべき栄養分も滞ってしまうので、同時に
脂肪もつきやすくなるのです。
「水滞」の改善方法についてお話します。
水太り 原因【水太りの解消と対策方法とは?】

「水太り」のほとんどの原因は、「水滞」です。
「水滞」とは漢方で、水(すい)の流れが停滞したために起こる病的状態をいいます。
体内に入った水が上手く排出されずに溜まって、これが身体に悪影響を及ぼしていると考えられます。
水分が必要以上に体内にとどまっているわけですから、体重が増えるのは当たり前です。
「水滞」になると、水分ばかりか、からだの各器官に行き渡るべき栄養分も滞ってしまうので、同時に脂肪もつきやすくなるのです。
ときおり、ヤセたい一心から、利尿剤を飲んで体重を減らそうという人がいますが、一時的に水分を外に出しても、「水滞」の根本的な原因を改善しなければ、結局は同じことのくり返しです。
しかも、利尿剤を服用しつづけると、腎機能の低下など、副作用に悩まされることになりますから、こうした無茶な方法は絶対に避けるようにしてください。
水滞の改善方法は、冷たい飲み物は控える、体を温める食べ物をとる、軽い運動をする、ツボ押しやリンパマッサージなど、体の巡りをよくすることがポイントです。
あと、サプリメントで、巡りを高める事も、水滞の改善のひとつです。
水滞を改善するサプリメントでオススメなのが、「めぐりゆく」です。
「めぐりゆく」は、体内に溜まった余分な水分を流してくれます。
大切な体内の水分のめぐりが悪くなったり、濁っているなら、一度、体の中の水分を見直す「めぐりゆく」をお試ししては如何でしょうか?
「水滞」を放置していると、水太りや、むくみなど、特にむくみを放置すると、セルライトが付きやすくなり、さらに皮下脂肪が付くので、ダイエットしても痩せにくい体質になってしまいますので、早めの対応が必要です。
もっと詳しく「めぐりゆく」について知りたいなら、こちらのサイトを参考にしてください。
余分な水分と塩分をキレイに流しましょう。
むくみを解決するためには、塩分を排出するだけではなく、水分代謝を健全にすることにより、
水分、老廃物が排出でき、また血流も改善、抗酸化作用により、根本原因の解決に繋がります。
公式サイトでは、お得ならくらく定期便を用意しています。 << 詳しくはこちら>>
水太りのダイエット!オススメ食品
積極的に食べたい「水」の食材
「水太り」タイプのダイエットにおすすめの食品は、野菜、果物、豆類など、水分を多く含む食材が中心。
「水太り」に水分?、と首を傾げる方もいるかもしれませんが、お茶や清涼飲料水をがぶ飲みする代わりに、これらの食材から水分を補給することが、利尿作用を高め、水分の代謝をよくするポイントなのです。
【キュウリ】
主成分……ブドウ糖、葉酸、カリウム、ビタミン132、Cなど。
キュウリの成分のうち、90パーセントは水分。栄養価値そのものには、とりたてて目立ったものはありませんが、余計な水分を体外に出してくれる利尿作用にすぐれています。
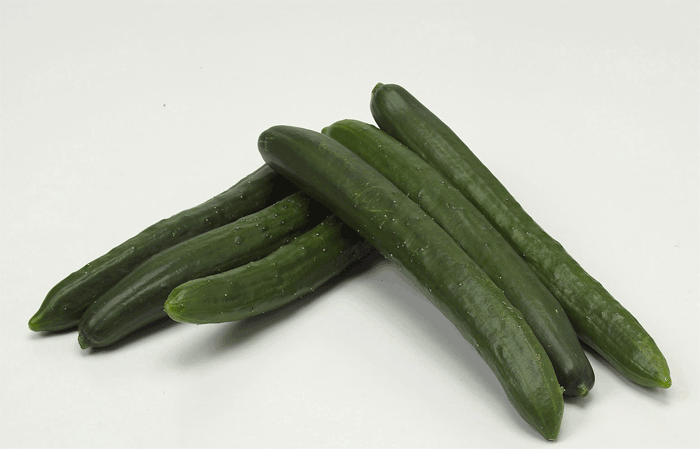
ただ、キュウリはからだを冷やす「寒性」のはたらきが強いので、下痢気味の人、冷え性の人は、生食は避けるようにします。
日本では、キュウリに火を通す調理法はあまりなじみがありませんが、トマトなどといっしょに煮込むイタリア料理や 炒めものの材料として使う中華料理などを参考にするとよいでしょう。
キュウリの利尿作用も、火を加えることによってさらに強まるといわれています。
【セリ】
主成分……精油、多種のアミノ酸、たんぱく質、ビタミンB1、B2、カルシウム、リン、鉄など。
「春の七草」の一つ、セリも、利尿作用にすぐれた食材。また、ヒステリー球といって、ストレスから、ヽのどに何かがひっかかった感じのする症状にも有効なので「気」の流れに問題がある人にもいいでしょう。
高血圧や肝機能を改善するはたらきもあります。
「水」に効くその他の野菜類……大根、ハクサイ、トマト、トウガン、など。
●魚介、海草類
【コイ】
主成分……たんぱく質、脂肪、カルシウム、リン、鉄、ビタミンB2、ニコチン酸、組織たんぱく氷解酵素など。
その高い利尿効果は、漢方薬としても利用されるほど。母乳の出をよくするはたらきもあるので、妊娠中や授乳中の女性にもおすすめしたい食品です。
【フナ】
主成分……たんぱく質、アミノ酸、カルシウム、リン、鉄、ビタミンA、B1、B2、カロチノイドなど。
コイ同様、利尿作用と乳汁不足に効果があります。また、胃腸を温めるはたらきがあるので、お腹が冷えやすい人にとくに適しています。
「水」に効くその他の魚介、海草類……アサリ、ハマグリ、タニシ、ハモ、など。
●肉類、卵、牛乳、穀類、豆類
【アズキ】
主成分……たんぱく質、脂肪、デンプン、サポニン、カルシウム、リン、鉄、チアミン、リボフラビン、ニコチン酸、ビタミン剔、B2など。
アズキのむくみをとるはたらきは古くから知られ、民間療法にもよく用いられています。
繊維質が多く、皮下脂肪の蓄積を防ぐ作用もあるので、「水太り」タイプのダイエットには、心強い味方といえるでしょう。
しかし、いくらアズキがダイエットによいからといって、甘いおしるこやアンコばかり食べていれば、意味がありません。
ダイエット用には、やわらかく煮たものをご飯の代わりに食べたり、1日30グラムのアズキを500ccの水で30分ほど煎じた汁を、1日2~3回に分けて飲むことをおすすめします。
また、長期間アズキを常食すると、皮膚が乾燥しますので、肌をうるおす作用のある「水」の食材、ハトムギといっしょにとるようにするとよいでしょう。
【モチ米」
主成分……たんぱく質、脂肪、炭水化物、カルシウム、リン、鉄など。
からだを温める作用が強いので、「水太り」タイプに多く見られる、冷えからくる下痢によく効きます。
疲れやすく、よく寝汗をかく人、夜中に何度もトイレに起きる人にもおすすめ。
ただし、利尿を抑えるはたらきがあるので、むくみのある人や、膀胱炎、リウマチ、ゼンソクの症状がある人は避けてください。
【ハトムギ】
主成分……脂肪油、たんぱく質、ステロール、アミノ酸、でんぶん、ビタミンB1など。
健康食品としておなじみのハトムギは、利尿作用にもすぐれています。手軽に手に入るハトムギ茶を、ふだんからお茶代わりに飲むとよいでしょう。
また、ハトムギの殼をむいたヨクイニンは、医薬品としても認められています。
肌にうるおいを与えて美しくする作用もあるので、ご飯に混ぜて炊いて食べることをおすすめします。
「水」に効くその他の肉類、卵、牛乳、穀類、豆類……クロマメ、大豆、エンドウ、玄米」、トウモロコシの毛(煎じて飲むと利尿に効果的)、など。
●果実、種実類
【スイカ」
王成分……アラニン、アルギニン、ブドウ糖、ビタミンC、リン酸、カロチン、カリウムなど。
ウリ科の植物は、一般に利尿作用にすぐれたものが多いのですが、スイカもまた然りです。
スイカの汁を煮て凝縮したものをスイカ糖と呼びますが、これを作っておけば、スイカのない季節にも活用できて便利。
作り方は簡単で、果肉をタネごと砕いて鍋に入れ、しばらく煮たらガーゼで絞り、その汁をさらにアメ状になるまで煮詰めます。
これを食後にスプーンー杯ほど飲むどよく、ビンに入れて冷暗所におけば保存がききます。
【バナナ】
王成分……炭水化物、たんぱく質、脂肪、カロチン、糖、カルシウム、リン、カリウム、ビタミンA、B、C、Eなど。
バナナは、スポーツ選手が、運動の合間の栄養補給などにもよく利用する、消化吸収にすぐれた食品。
とくに利尿作用があるわけではありませんが、腸をうるおすはたらきがあるので、「水太り」タイプの中でも、便秘がちな人におすすめです。
「水」に効くその他の果物、種実類……柿、モモ、ミカン、ナシ、メロン、キウイ、など。
「水太り」タイプのダイエットには、以上のような「水」の食材をすすんでとるようにすると同時に、当然、水分のとりすぎにも注意しなくてはなりません。
味付けの濃い料理や、油っこい食事は、あとでのどか渇くので控えめに。
また、のどか謁いたときは、飲み物ではなく、なるべく果物から水分をとるようにしたり、水を口の中にふくむ習慣をつけるだけで、水分の摂取量はかなりちがってくるものです。
水太り対策と健康のために!!
むくみを解決するためには、塩分を排出するだけではなく、水分代謝を健全にすることにより、
水分、老廃物が排出でき、また血流も改善、抗酸化作用により、根本原因の解決に繋がります。

水太りを解消するための、生活改善アドバイス

【汗をかくなら、サウナよりスポーツで!】
「サウナでたくさん汗をかけばヤセられる」「水太り」タイプでなくとも、多くの入はこう考えていらっしやると思います。
が、はっきりいって、サウナはダイエット法としては、あまり効率的ではありません。
サウナに入るとヽたしかに一時的に体重も減りますが、これはからだの表面に近い部分にある水分が汗として出ただけなので、水分の代謝を高めるという点ではさほど効果かおりませんし、サウナあとで水分をとれば、すぐにもとに戻ってしまうものなのです。
さらにヽ水分としてヽジュースやアルコール類をとれば、かえって太る、という結果になりかねません。
同じ水分をからだの外に出すのなら運動がいちばんで、それも激しいスポーツより、長い時間かけて汗をかくジョギングなどが適しています。
【美食や飲みすぎも「水太り」には禁物<】
いくら汗をかいても、一方で水分をとりすぎては意味がありません。
運動中は、脱水状態にならないためにも、多少の水分補給は必要ですが、それ以外のときはできるだけお茶
や清涼飲料水をひかえ、水分は果物などからとるように心がけましょう。
美食や飲酒も、「水大り」タイプの方は、ほどほどにする必要があります。
若い女性に人気のフランス料理やイタメシは、もともと高カロリーな上、脂っこく、デザートにはたっぶりと砂糖やクリームが使われていますが、こうした脂肪分や甘いもののとりすぎは、からだの水分代謝を狂わせる大きな要因となるのです。
アルコール類もまた、意外にカロリーが高いものですし、知らず知らず多量の水分をとってしまうものなので、飲みすぎないことが肝心。
外食をする際には、あっさりとした和食を中心に、お酒はビールの小瓶一本とか、グラスワインー杯というように、できればあらかじめ飲む量を決めておくようにしましょう。
【寝るときには足を高くする】
家庭では寝るときにもむくみ解消のポイントがあります。
軽いむくみであれば、通常は一晩寝れば解消され ますが、なかには完全には解消されない入もいるでしょう。
また、足にむくみやだるさがあれば横になっ ても寝つきが悪いかもしれません。
就寝中にむくみをしっかり解消させるには、重力 を利用してむくみを軽減する目的で、足元に座布団や枕を入れて足を15mくらい高く(心臓よりも高く して血液・リンパ液が心臓に戻るのに重力を利用し ます)して寝るとよリ効果的です。
この場合には、かかとの下だけでなくひざの下くらいまで座布団な とを入れて、下腿全体が高くなるような工夫をするとよリ効果的です。
【入浴後に適度なマッサージを行う】
むくみの実態調査で効果が高かったむくみ解消法は「自分でマッサージやツボ押しをする」、「お風呂
や足湯で温める」でしたが、これらも実際に筑果があります。
マッサージは、基本的には足の指のほうから心臓方向に向かって行います。
入浴や足浴でからだが温まって血管が拡張した状態で行うとよリ効果があります。
ただし、マッサージをする際に皮膚に摩擦が強く生じると、皮膚がダメージを受けてしまいますので、マッサージをするときには手や指が皮膚をすベリやすくするためにクリームやオイルなどを利用するとよいと思います。
水分のとり方で、水太りを防ぐ!

【温かい飲み物を選ぶよう心がける】
飲み物を飲む場合、特に暑い日や運動などで汗をかいたときでなければ、摂取量は1日1ℓ前後後を目安にすればよいでしょう。
ふだん、リラックスタイムや食事のときにとる飲み物は、できれば冷たいものより温かいものを選ぶようにします。
冷たい飲み物はのどごしがよく、一気に飲めるため、それはどのどか渇いていなくても、ついたくさん口にしがちです。
暑い昼間にガブガブ飲んでしまう結果、涼しい夕方になると、その水分が体にたまってむくむということが少なくありません。
また、冷たい飲み物は体を冷やしてしまい、血行を悪くさせる恐れもあるので、とりすぎは禁物です。
【ひと口ずつゆっくり飲む】
のどか渇いていると、ついゴクゴクとたくさん飲みたくなるもの。
けれど、渇いたのどを潤すためには、必ずしも大量の水分は必要ありません。
飲み物を飲むときには、どんなものでも一ロずつ口に含み、口の中全体に行き渡らせる、あるいは水をかむような感じで、ゆっくりと飲みます。こうすれば、少しの水分でも、渇いたのどか潤います。
注意したいのは冷たい飲み物。
一気に飲むと、「のどか潤った」と感じる前に、水分をとりすぎてしまいます。
温かいお茶などをゆっくり飲めば、のどの渇きもいやせ、ゆっくりリラックスできます。
【アルコールは適量を守る】
アルコールには血液の浸透圧(水分をしみ込ませる力)を上げる作用があり、血管の外に水分が出ていきやすくなります。
そのため、お酒を飲んだ翌朝はむくみやすいのです。
一方、アルコールを飲んだ翌朝は、とてものどが渇きます。
アルコールの作用で、血管の外に水分がしみ出したり、アルコールの持つ利尿作用によって、尿の量が多くなります。
すると、体の中を流れる血液の量が少なくなるため、脳から「水分をとるように」とサインが発せられるのです。
アルコールとは、節度あるつき合いを心がけ、アルコールを飲んだ翌日は、刺激の少ない温かい飲み物を飲んで、適度に水分補給をしておきましょう。
また、むくみを解消させるための運動も欠かせません。
【日中は多めに、夜は少なめに飲む】
昼間は、夜に比べて体を動かす量が多いもの。活動量が多いときは、自分では気づかなぺても、けっこう汗をかいているので、昼間は水分の補給は多めでもかまいません。
反対に、活動量が少なくなる夜間は、飲み物の量を少し控えめにしたほうがよいでしょう。
水分を多くとりすぎると、翌朝にむくみを起こす原因にもなります。
ただし、夜間にあまり水分を控えすぎるのも問題です。
水分が不足すると、睡眠中に血液が濃くなって、極端な場合では、血栓(血液の塊)ができやすくなります。
特にお年寄りは、睡眠中にトイレに起きるのがやっかいなため、つい水分を控えてしまいがちですが、とりすぎない程度に水分をきちんととっておくことが大切です。
むくみ・水太りを改善する、ふくらはぎのケアの方法

「気」の流れにそくしてさすることで「血」「水」の循環も自然とよくなる
東洋医学では、体内を「気」「血」「水」という3つの要素が、バランスよくスムーズに体内を循環していることで、心身が健康に保たれると考えています。大まかにいうと、血=血液、水=リンパ液などの体液と理解してもよいでしょう。この血と水を動かすのが、「気」という生命エネルギーにあたります。
この「気」の流れにそくして「さする」ことで、気の滞りをなくす働きがあります。
「気」の流れがスムーズになれば、「血」「水」の循環も自然とよくなり、健康になるということです。
「さする」行為では、心地よい圧力でさする方法と、触れるか触れないかという非常に軽い方法があります。
軽いと効果が薄そうな感じがしますが、だいじょうぶです。
部位によっては、強く触られると何ともないのに軽く触れられるとくすぐったい、ということがあります。
そんな風に軽い刺激にもきちんと個性があるのです。
血行促進や新陳代謝の改善につながる、ツボ押しを上手に取り入れた体作りを
「押す」方法ですが、ツボ上に限っては少し強めに押してください。
そして押した後は、引く行為にも集中してみてください。
「押す」という刺激に負けず、実は「引く」という刺激にも意味があります。
そして、できるだけゆっくりと引いてみてください。
ただし、あまり長く押し続けたり、強く押しすぎると、かえって筋肉や神経を痛めたりすることもありますので、ほどほどに行うことが大切です。
心地よい刺激を与えることがいちばんです。
手のひらで円を描くようにもんだり、圧を加えたまま上下に揺するなど刺激を
「もむ」場所は「押す」場合より広範囲になると思いますので、ツボを中心に手のひら、もしくは第一指から第四指を揃えてもんでください。
手のひらで円を描くようにもんだり、圧を加えたまま上下に揺すってみたり、左右に揺すってもんでみましょう。
「もむ」ためには、床に座りながら、立ちながら、いすに座りながらといくつかの方法があります。
部位によって違うこともありますので、ご自分のやりやすい方法を見つけてください。
