
腸の免疫力を高める【腸の壁をきれいにすれば免疫力がアップ】
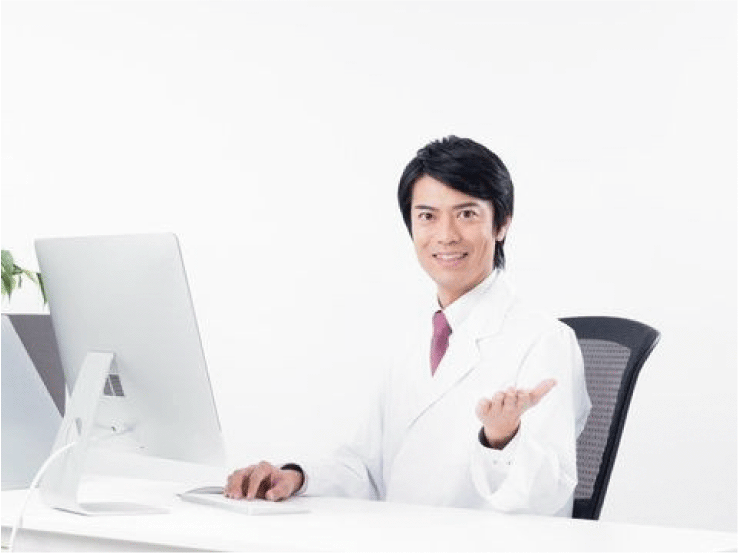
なぜ便秘になるのか。それは、腸の免疫力が落ちているからです。
私たちの腸には、100種類100兆個もの細菌がすみついています。大別して体にいい影響を与える「善玉菌」、悪い影響を与える「悪玉菌」の2種類がいます。
ほかに、少数ですが「免疫力が低下すると悪いことをする日和見菌もいます。
腸内細菌の総量はほぼ決まっていて、善玉菌がふえれば悪玉菌が減り、悪玉菌がふえれば善玉菌は減ります。
善玉菌が多ければ、腸は若々しく保たれますが、悪玉菌が多ければ、腸は老化して健康にも悪影響を及ぼしてしまいます。
善玉菌には、次の働きがあります。
・病原菌の活動を封じ込めて、感染病から身を守る。
・腐敗菌の増殖を抑え、腸内の汚れをとる。
・乳酸や酢酸などの有機酸(酸の特性をもつ化合物)をつくりだして、便秘を防いだり腸の吸収力を高めたりする。
・免疫力を強化して、体の抵抗力を高める。
・下痢の予防と治療をする。
・発がん物質を分解する。
こうした働きをもった善玉菌が減って、悪玉菌がふえれば、便秘や下痢、食中毒などを引き起こしやすくなるだけではありません。
免疫力が低下するので、糖尿病や高血圧からがん、カゼなどさまざまな生活習慣病をまねいたりするのです。
腸内細菌の種類や数は、年齢とともに変化します。回威を過ぎてくると、腸内細菌の分布図は善玉菌優勢から悪玉菌優勢へと、その絵が塗りかえられてしまいます。
すると、腸内環境が悪化し栄養素の吸収も低下するため、食べたものが未消化で大腸へと送られることになります。
高齢者が便秘を起こしやすいのは、このためです。
腸内環境を決定する2つの菌

腸の壁の内側には、たくさんのひだがあり、消化された食物の栄養素は、このひだから吸収されていきます。
ひだの内側には100種類、100兆個ともいわれる腸内細菌がすんでいて、「フローラ」という群れをつくっています。
腸内細菌は、「善玉菌」「悪玉菌」と、腸の状態によって善玉・悪玉のどちらにも変わる「日和見菌」とに分かれます。
善玉菌の代表格はビフィズス菌、悪玉菌の代表格はウェルシュ菌、大腸菌などです。
善玉菌は、腸の嬬動運動を活発にして自然な排便を促したり、ビタミンを合成したり、免疫力を高めたりして、体を健康にします。
悪玉菌は、嬬動運動を鈍らせたり、消化器の消化吸収力を弱くしたり、腸の中で腐敗物質や、毒素、発がん物質などをつくったりします。
腸の中で善玉菌と悪玉菌は絶えず勢力争いをしています。
ヨーグルトやぬか潰けなど乳酸菌の多い食品や、オリゴ糖や食物繊維の多い食品をとると、善玉菌が増えてきます。
適度の運動や、リラックスした心理状態でも、善玉菌が増えてきます。
善玉菌が多くなると、腸の中が酸性になって、酸性の嫌いな悪玉菌がすみにくくなります。
一方で、肉食で動物性タンパク質や動物性脂肪をたくさんとると、腸の中に悪玉菌のウェルシュ菌などが増えて、悪玉菌優位になります。
ストレスの多い生活や睡眠不足、風邪などの病気でも悪玉菌が増えてきます。
腸の中に悪玉菌が増えると、腸の活動が鈍くなって、便秘、下痢、おなかの張りなどが出てきます。
また、悪玉菌が出す毒素が血液中に溶け込んで、治りにくいニキビや肌あれ、口臭、頭痛などが出てきます。
悪玉菌は、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどの重い大腸の病気の原因にもなります。
便秘には3つのタイプがある

現在、便秘で悩んでいる人は、日本中でおよそ500万人いるといわれています。
しかし、潜在的には約800万~1000万人が便秘に悩んでいると推定されます。
特にダイエットなどで食事の量を減らしている若い女性と、腸の働きが低下した60歳以上の高齢者に多くみられます。
一般に、「2~3日に一度排便があれば便秘ではない」といわれていますが、2~3日に一度排便があっても、また「おなかが張る」「おならが臭い」などの自覚症状がある人は、たとえ毎日排便があっても、腸の中に古い便がたまっていて、腸内環境が悪くなっていますから、便秘の人と同様に生活を見直すことが大切です。
【便秘は次の3つに分類できます。】
①ほかの病気が原因で起こる便秘……大腸がんや腸管狭窄・閉塞、脳腫瘍や脊椎損傷などの中枢神経障害、高カリウム血症、高カルシウム血症、脱水などの病気が原因で起こる便秘です。
②生活習慣が原因で起こる便秘……不適切な食事内容やストレス、下剤の乱用などによって起こる便秘です。ほとんどの便秘はこのタイプで、さらに次の3つに分けられます。
・弛緩性便秘……食事をとる量が少ない、嘔吐、発熱、脱水、寝たきりなどによる筋力の低下、便意をがまんする、環境の変化などによって、結腸全体の運 動機能が低下して起こります。
・けいれん性便秘……精神的ストレス、うつ痢などによって結腸の緊張が異常に高まって起こります。下痢と便秘を繰り返すのが特徴です。
・直腸性便秘……直腸まで便が下りてきているにもかかわらず、便意が起こらないために便秘になるタイプです。下剤や淀腸の乱用、腹筋力の低下などが原因で起こります。
③薬が原因で起こる便秘……抗コリン薬、利尿剤、抗がん剤、モルヒネ、麻酔剤などの薬が原因で起こる便秘です。
