
<目次>
・受験生の食事【受験生に必要なのは毎日の食事だった!】
受験生の食事【受験生に必要なのは毎日の食事だった!】

脳の栄養管理が、大学受験生の重要なカギになります。
脳の栄養管理とはすなわち、私たちが毎日の生活の中で行っている食事にほかなりません。
ちまたでは、頭をよくするために、いくつも塾通いをさせるなど、並々ならぬ努力を重ねている家庭も多いようです。
しかし、肝心の脳をつくるための栄養管理ができていなければ、どんな努力も実を結びません。
朝食抜きは大学受験生の脳の栄養失調を招く
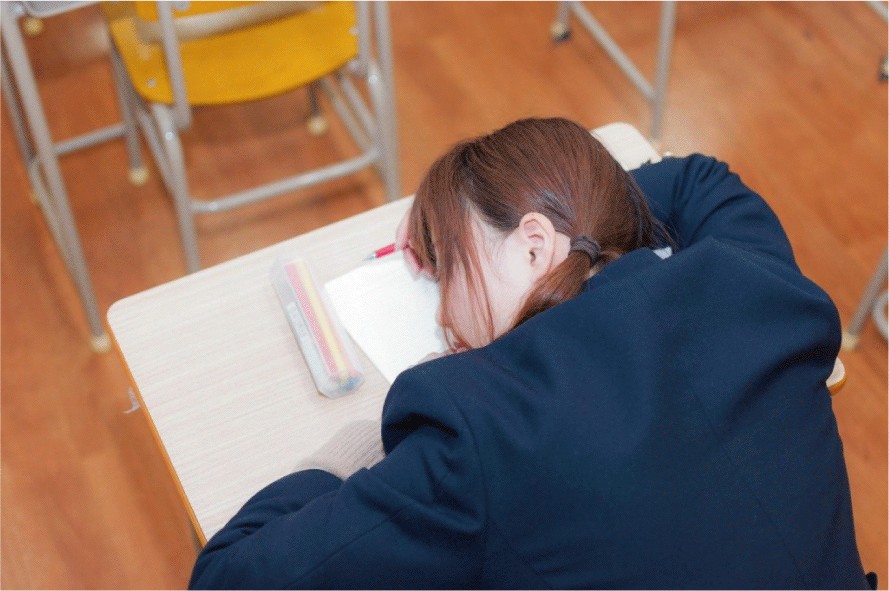
すっきり目覚めた朝は、自然におなかがすきますね。
なぜだかおわかりになりますか?
私たちの体は、脳の中にある生物時計の指令を受けて生活のリズムを刻んでいます。
ヒトの体の中には、約25時間を周期とした時計があり、その時計は、地球の自転による明暗サイクルを受けて、常に、周期を24時間に修正しています。
この生物時計が、午前4時頃から副腎皮質刺激ホルモンや、代謝に関連する酵素の分泌の増加を命じるため、私たちの体は栄養を受けとる準備を始めます。
つまり脳と体は、目覚める前から栄養補給を心待ちにしているのです。
しかも、脳は眠っている間もエネルギーを消費しつづける臓器なので、朝起きたときにはエネルギーを使い果たしてガス欠状態。
そのまま朝食を食べずに1日をスタートすると、脳は確実に栄養失調になり、十分に機能させることができません。
朝食の有無による学習効率の調査研究はいろいろと行われています。
そのひとつ、アイオワ大学の9~11歳の学童に対する調査では、朝食を食べるグループのほうが、食べないグループよりも授業に熱心であり、学業成績もよく、特に午前中のテストでは高い平均点を得たとの結果が出ました。
このことからも、大学受験生の脳には朝食がたいせつであり、特に、授業や受験が行われる時間帯の学習効率を上げるためには欠かせないことが、おわかりいただけるでしょう。
学習に必須の栄養素をバランスよく凝縮!
DHA・EPA500mg、ホスファチジルセリン200mg、GABA30mgの3大成分を贅沢に配合!記憶力を高めるサプリメントの中でも抜群かつ最適な配合量を実現!
公式サイトでは、毎月100名様限定 50%OFF!ず~っとお得な定期コースを用意しております。 詳しくはこちら>>
規則正しい食事が大学受験生の脳の働きを活性化させる
なぜ、食事は朝、昼、晩と規則的にとらなくてはいけないのでしょうか?
謎をとくカギは生物時計にあります。
生物時計は、朝ごはんだけでなく、1日の摂食行動全体にも大きく関係しているのです。
常に餌を食べているラットも、摂食行動を観察してみると、食べる量が増加する時間帯は私たち人間の食事パターンとほぼ同じ、1日3食です。
脳内の生物時計が、時刻情報ともいうべき情報を体内に流して、摂食行動をコントロールしているのです。
時刻情報とは、脳ヘブドウ糖が定期的に届くように調節する役割を担った情報のこと。
具体的には、刺激を受けると空腹を覚える摂食中枢や満腹感を感じる満腹中枢に影響を与えたり、血中のブドウ糖を高めるグルカゴンや、遂に血糖を低下する作用のあるインスリンなどの分泌にかかわったりしています。
生物時計のコントロールのもと、ある一定の食事時間が習慣化すれば、インスリンの分泌もよく、栄養代謝が活発になります。
インスリンの分泌は脳に直接影響を与えるものではありませんが、食間の脳へのブドウ糖供給源となる肝臓のグリコーゲンの合成を促し、結果、脳へ栄養が届きやすくなります。
逆に不規則な食事は、消化、吸収、代謝の規則的なリズムを刻めないために栄養の効率も悪く、ひいては脳へ送られるエネルギーも低下してしまいます。
要するに、私たちの体は、地球の自転による日内変動を基準に、1日3回、食事をするように義務づけられているのです。
大学受験生は、夜と昼の逆転する勉強より、規則正しい生活スタイルで勉強をする方が、脳が活性化し、記憶力アップにつながることになるのです。
一度購入された方からのリピート率は97.4%と驚異的
集中力を上げ、記憶力を上げるサプリメントとして、受験生のお持ちのお母さんから大好評のサプリメントです! もっと詳しく知りたい方は…

受験生には間食で脳に必要な活力を維持させる!
「受験生のレシピ(子どもの能の力を120%引き出す合格料理)」の本を読んで、娘の受験時に実行してみた。
結果から言うと、グンと学力テストの点数が伸び、無事第一志望の学校に合格しました。
この本に書いてある、何が脳に対して良い栄養素なのか。どんな食事をすれば脳にマイナスなのか。参考になった「脳の活力を維持させる間食のとり方」の部分を抜粋して紹介します。
受験生に必要なエネルギー補給に役立つ間食

食生活の基本は、バランスのとれた食事を1日3回とること。脳へ送るエネルギーも、3度の食事からとることが理想です。しかし、1日中、脳を働かせている受験生は、3食では足りない場合もあります。
私たちの体は″生物時計〃などの慟きによって、血糖濃度が常に一定に保たれるような仕組みになっていますが、厳密にいえば、食事直後と次の食事の間とでは、血中濃度に差が出てしまうのです。
食間の空腹時には、食事直後の満腹の状態とくらべると、20%も血中濃度が低下してしまいます。もちろん、その分、脳へのブドウ糖供給率も低くなります。
よく、「おなかが減りすぎてなにも考えられない」などと、授業中にこぼしている学生かいますが、血中濃度が低下していると考えれば、当然なことだといえるでしょう。
そんなとき甘いものを食べると、体内の血糖濃度が高まり、脳ヘエネルギーが供給されます。
ですから、甘いものイコール虫歯や肥満の原因、などと決めっけないでください。
砂糖の成分の半分は脳のエネルギー、ブドウ糖です。極端にとりすぎない限り、脳に対する価値は高いのです。
若年性糖尿病や心疾患のために食事療法をしている場合以外は、砂糖をじょうずにとり入れたおやつを食べさせることも、脳の活力を保たせるために重要なことです。
勉強だけじゃ駄目!学習アップ栄養補給!!
受験生特化型サプリメント!6粒にお子様の脳の発達などに役立つ栄養素である「DHA・EPA」を500mg配合しており、厚生労働省が定める一日推奨量の半分以上を補ってくれます。
公式サイトでは、特別価格にて用意しています! 詳しくはこちら
受験生の勉強意欲を奪う!間食とは!

ハンバーガーにカップラーメン、スナック菓子……どれをとっても身近にあって、おやつとしては手軽なものです。けれど、これらをひとくくりにして別の名前がつけられているのをご存知ですか?
お聞きになったことがあるかもしれませんが、「醒化食」といいます。
脂肪分が多く、しかも油が古くなって酸化していることからつけられた名前です。
酸化した油は、脳細胞にふれると細胞壁を破壊し、脳の働きを鈍くします。
どんなに3回の食事に気づかっていても、おやつや夜食に酸化食を食べていては、その努力が水の泡。
そればかりか、勉強をつづけるやる気や根気まで奪ってしまう可能性もあるのです。
受験生の脳が活性化する!間食とは!
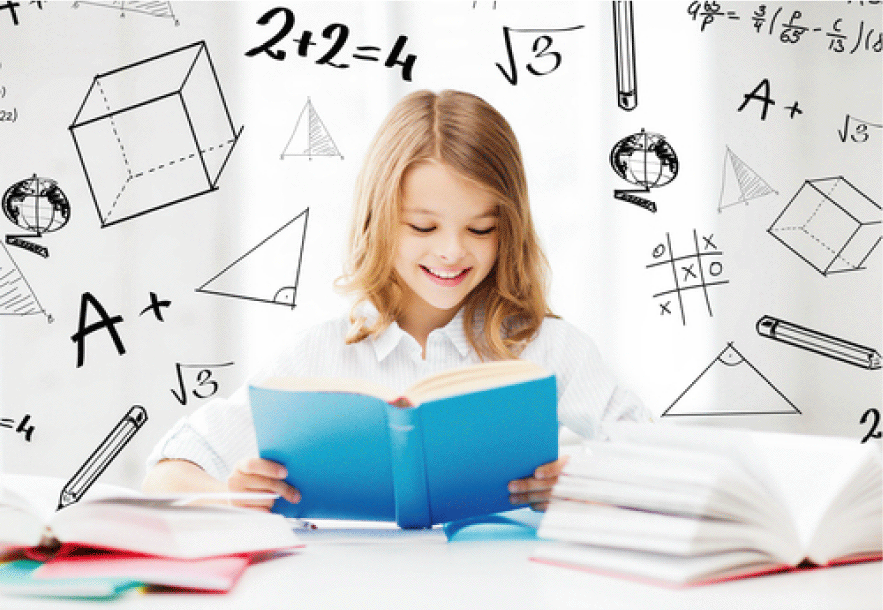
おやつや夜食は、次の食事までのエネルギーを補給するもの、と考えるとわかりやすいでしょう。
できれば、脳にも体にもよい食材を使った手作りのおやつや夜食を食べさせたいものです。
手軽に作れる飲み物でもよいでしょう。
牛乳や果汁100%のオレンジジュースに、キャンディ1~2個を添えるといった程度でも効果があります。
コーヒーや緑茶には、脳機能に必要な鉄の吸収を阻害するタンニンが含まれます。
高校生くらいの、脳の成長が終わっている年齢であれば問題はないのですが、脳が発育する時期にあたる幼年別の子どもには控えてください。
また、チョコレートはポリフェノールが多いので、白血病の原囚になることも。食べさせるならポリフェノールをほとんど含まないホワイトチョコレートをおすすめします。
おやつや夜食は、差し人れる人の愛情を格段に感じさせます。
それはどんな栄養にも勝り、勉強への意欲を高めてくれるのではないでしょうか。
勉強だけじゃ駄目!学習アップ栄養補給!!
受験生特化型サプリメント!6粒にお子様の脳の発達などに役立つ栄養素である「DHA・EPA」を500mg配合しており、厚生労働省が定める一日推奨量の半分以上を補ってくれます。

