
「自宅の土地」への増税は、すでにこっそり実行されているって知ってましたか?
相続する土地の8割引で相続税を計算する特例が、H22年以後に亡くなった人の相続から適用を受ける要件が厳しくなりました。
このサイトでは、不動産にかかる莫大な相続税を支払う前にやっておきたい、相続税対策について詳しく解説しています
・生前贈与は「贈与する人は多く」、そして「長い期間に」が鉄則
生前贈与の不動産をかしこく贈与するには!

不動産を相続する時は、相続時精算課税制度を使って相続すれば税制対策になるといわれます。
実際、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までは非課税なるのですが、2015年の法改正により、さまざまな制度・特例を吟味して考えていかないと余分な相続税を支払うことになります。
2015年の法改正では、基礎控除の金額がH26年12月31日までは5,000万円+(1,000万円×法定相続人)に、H27年1月1日以降は3,000万円+(600万円×法定相続人)に改正されます。
しかし、贈与税も改正され、贈与時精算課税の適用範囲の拡大と贈与税の税率構造も6層構造から8層構造へ区分が新設するされるなど、贈与税の緩和が行われます。
さらに、小規模住宅等の特例では、改正前は240㎡までの宅地面積は税金の金額の80%が減額対象でしたが、今回の改正によりこの広さが330㎡にまで拡大されました。
今回の法改正で、今まで課税されなかった人でも土地建物が課税の対象になる可能性がでてきました。
土地や建物は課税対象になりやすいので、事前に贈与という形で相続していくことが賢明です。
住宅取得時に親から多額の贈与を受ける場合や事前に親の不動産を相続する場合は、専門家に相談することをお勧めします。
自宅の不動産を8割引きで相続する方法とは!

「自宅の8割引特例」とは、亡くなった人の自宅の土地は、一定の面積330㎡(100坪)まで、8割引で相続税を計算できるという特例です。もし、自宅の土地が1億円なら、相続税の計算上は2000万円になります。
この特例は「小規模宅地の評価減の特例」といい、H22年4月1日以後に亡くなった人の相続から適用を受けることになります。
しかし、実際には小規模宅地の評価減が使えないことも多く、予想外の高額税負担となることも多いのです。
もし、自宅をお持ちで相続税負担が予想される方は、この特例が使えるかどうかをあらかじめ検討されることが重要です。
では自宅の土地を8割引で相続するには、どんな要件が必要でしょうか。
1)「亡くなった人」が住んでいた自宅の敷地である
2)同居親族・・・持ち続け、住み続ける
3)マイホームを持たない別居親族・・・持ち続ける(住まなくてもOK)
実は、従来は、要件1を満たせばその段階で5割引、さらに、要件2を満たせば8割引になりました。しかし、改正により5割引は廃止され、たとえ「亡くなった人」が住んでいた自宅の土地でも、要件の1)2)3)の人が「もらった」場合だけが8割引、それ以外は割引なしになったのです。
まず、第一に「亡くなった人がその土地の上にある建物に、亡くなる瞬間に生活の拠点を置いていたかどうか」で判定します。
両親や夫が長年暮らしていた自宅なら、「亡くなった人判定」を難なくクリアできますが、病院に長期間入院していた・老人ホームに入った・持ち家が二つある場合などは判定が難しくなります。
しかし、8割引が使えなくても、土地やその上にある建物を人に有償で貸していると、その土地が「5割引」になる特例もあります。
このように、自宅の8割引特例が使えなくなりそうなら、親の自宅を親がまだ生きている間に人に貸せば、5割引特例が使えるのです。
不動産の相続に関しては、一刻も早く専門家に相談することです。
不動産で生前贈与するデメリットとは!

不動産を生前贈与するデメリットとして
1)不動産の価格によっては贈与税が高くなる場合がある。
2)不動産取得税がかかる。
の2つが上げられます。
その中でも一番のデメリットは贈与税率が高いということです。
環境や経済などの動向により、土地の評価は変動します。贈与税は路線価評価額で算出されますので、相続の時期が難しいのです。
後、不動産取得税以外にも不動産を贈与されたときの登記費用が発生します。
登記は義務ではありません。しかし、第三者に対して、もらった不動産の権利を得たと主張するためには、登記をすることが必要となります。
登記をしなければ、将来不動産の売却時令金融機関などへの借入の担保にすることもできません。
不動産の生前贈与を受けたときにする登記のことを「所有権移転登記」といいます。
手続き書類は次のようになります。
(ア)登記原因を証明する書類
登記をする理由がわかる書類を法務局へ提出します。たとえば、「不動産贈与契約書」です。
(イ)権利証
贈与される上地の権利証が必要です。
(ウ)印鑑証明書
あげる人の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)が必要です。
(エ)住民票
もらう人の住民票(有効期限なし)が必要です。
(オ)固定資産税評価証明書
市町村役場で申請すると固定資産税評価証明書(贈与年度のもの)がもらえます。
(カ)委任状
登記を司法書上等他人に依頼するときに必要です。
■贈与契約書の印紙税
土地などの不動産の贈与契約書にも印紙税を貼らなければいけません。
不動産の贈与も、「不動産の譲渡」に含まれますので、印紙税法の税金の対象となる文書に該当します。
その場合、納付する印紙税額は、贈与は無償の契約ですので契約金額の記載のない契約書として、200円
となります。
また、不動産贈与契約書に、たとえば「時価1億円の土地を贈与する」というように、贈与物件の評価額の記載があったとします。
その記載金額は実際の売買金額ではないため、印紙の金額は200円となります。
単純な贈与契約書では、基本的にあげる人(贈与者)の意思と、もらう人(受贈者)の意思がはっきりしていればよいので、なるべく単純に書いた方が無難です。
親に気持よく生前贈与の準備をしてもらうために!

相続について、家族で話し合うことって少ないですよね。まだ、親も元気だから相続なんてまだまだって思っている方も多いでしょう。
しかし、2015年1月に相続税法が改正され、相続税の基礎控除額が4割も少なくなったのです。
その分、相続税のかかる課税対象額が大きくなってしまいました。
相続税改正前は基礎控除額が5,000万だったのでですが、2015年1月の相続税法が改正後、基礎控除額が3,000万円になりました。
もし相続いする土地の評価が3,000万円とすれば、土地以外に建物、預貯金、株や投資信託などの有価証券類をお持ちであれば、基礎控除額を超えてしまうご家庭が意外とたくさんあるそうです。
今まででしたら相続税がかからないご家庭でも相続税がかかる時代になったということです!他人事ではありません!。
2015年の改正をひとことで言うと、「相続税は増税、贈与税は減税」です。「教育資金の一括贈与の特例」「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」がありますので、「贈与税」の特例を上手に活用することことで相続税対策となります。
2015年の改正について専門家と相談し、親にその旨を伝え、かしこく相続の準備に取り掛かることが重要なのです。
相続・生前贈与に関する相談窓口を無料で案内してくれる
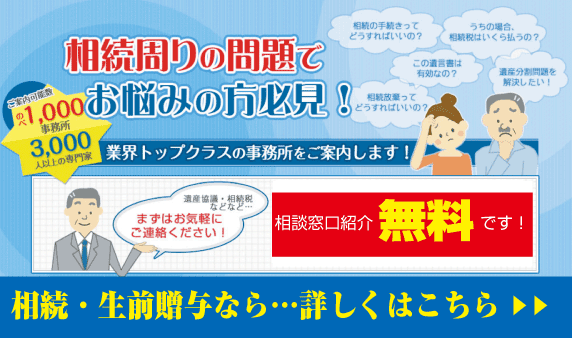
3,000名以上の専門家の中から、あなたの悩みにあった相談窓口を紹介! 詳しくはこちら>>
生前贈与と相続の分岐点を知っておこう!
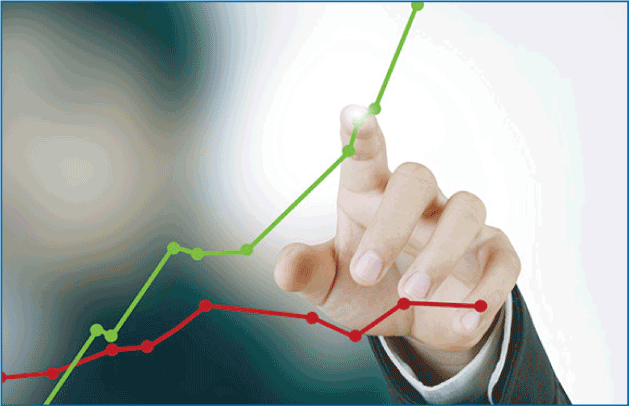
贈与の話をすると、ほとんどの方が「贈与税は高い」「贈与は損た」と思われている方が多いようです。
贈与税の税率だけを見ると、相続税の税率よりも高く設定されています。
しかし、税率だけを見て判断するのは、誤りです。
1.低い税率を使うことにより生前贈与を繰り返すと、相続税の節税になります。
2.贈与を正しく行うことで、「価値のある」財産を残すことができます。
上記2点を考慮し、生前贈与を検討してみるのもいいのではないでしょうか。
では、贈与の方が有利な額は、どのように計算するのでしょう。
相続税との比較において、相続税の実効税率(相続財産価額の合計額に対する相続税額の割合)と、贈与税の実効税率(贈与財産の価額に対する贈与税額の割合)とを比較し、贈与税の実効税率が相続税の実効税率を下回るところを「贈与分岐点」贈与の話をすると、ほとんどの方が「贈与税は高い」「贈与は損た」と思われている方が多いようです。
贈与税の税率だけを見ると、相続税の税率よりも高く設定されています。
しかし、税率だけを見て判断するのは、誤りです。
1.低い税率を使うことにより生前贈与を繰り返すと、相続税の節税になります。
2.贈与を正しく行うことで、「価値のある」財産を残すことができます。
上記2点を考慮し、生前贈与を検討してみるのもいいのではないでしょうか。
一つの考え方として、相続税より低い税率の範囲で行う事もありです。
では、贈与の方が有利な額は、どのように計算するのでしょう。
相続税との比較において、相続税の実効税率(相続財産価額の合計額に対する相続税額の割合)と、贈与税の実効税率(贈与財産の価額に対する贈与税額の割合)とを比較し、贈与税の実効税率が相続税の実効税率を下回るところを「贈与分岐点」といいます。
この贈与分岐点以下の財産を贈与すれば、贈与の方が有利となり、有効な対応策といえるでしょう。
また、「相続時精算課税制度」を選択して贈与するならば、相続まで評価額が一定だとしますと、有利・不利なく贈与できます。
しかし、現在のような経済環境では、
●贈与するものや贈与の時期
●贈与財産の価額と相続が発生すると思われる時期
●そのときの財産の価額
によって、どちらが有利であるかをよく検討したうえで、暦年課税制度か精算課税制度による贈与をするかを慎重に考えてみる必要があります。
あまり複雑な内容に関しては、専門家に相談することをオススメします。
生前贈与は「贈与する人は多く」、そして「長い期間に」が鉄則

相続では、財産をもらうことができる人は、法定相続人として限定されています。
しかし贈与は、配偶者・子ども以外の人にも財産をあげることができます。
配偶者・子ども・子どもの配偶者(嫁・ムコ)・孫に贈与することを検討してください。
たとえば、5人に贈与すればそれだけでも1年間で550万円も贈与できます。
10年間続ければ、5500万円もの贈与ができるわけですから効果は多大です。
したがって、できるだけ多くの人に贈与することにより、効果が出てきます。
また、贈与税は高いという先人観がありますが、1年間110万円までの基礎控除だけでも多くの節税が可能です。
一度に多額の贈与をすると贈与税が重くのしかかってきます。
600万円を一度に贈与すると、贈与税は、82万円です。
しかし、4年間に分けて600万円贈与すると、各1年間150万円の贈与になるので、贈与税は4万円4回の16万円で済みます。
したがって、贈与する人数は多く、そして長い期間に分けて実行すれば、非常に贈与はオトクです。
相続・生前贈与に関する相談窓口を無料でご案内してくれる
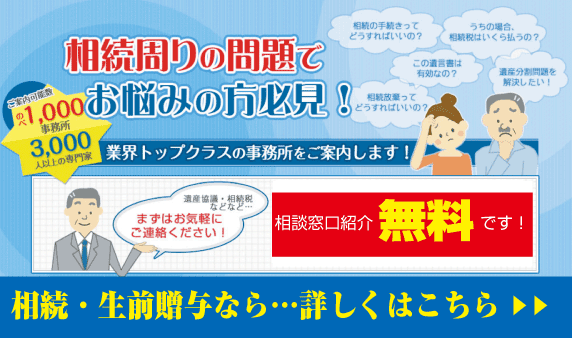
3,000名以上の専門家の中から、あなたの悩みにあった相談窓口を紹介! 詳しくはこちら>>
贈与税対策に贈与税を支払う?生前贈与対策とは

暦年贈与の場合、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば、税金がかかりません。
現金、土地や建物などの不動産、株式であれ、贈与する財産の種類が問われることはありません。
ただし、無税枠ぎりぎりの110万円の生前贈与を毎年繰り返していると、税務署によっては明らかな税金逃れとみなされることもあります。
このような場合は、110万円を超える贈与を行い、贈与税を納めることも1つの方法です。
特に、名義預金にならないためには有効です。
つまり、贈与税の基礎控除額(110万円)を超えて贈与を行い、税務署に申告をして贈与税を払って形に残すことです。
贈与税の存在意味は、たとえば生きているうちに財産を全都子や孫にあげると、親が死亡したときに財産がなく、一切相続が発生しないことになります。
そこで、相続税が課税されないという事態を防止するために、つまり相続税を補完するために贈与税があるのです。
贈与税の手続きは、以下のようになります。
①申告者
財産をもらった人が申告します。
②申告場所
もらった人の住所地の税務署が申告場所です。たとえば、もらった人が大阪に住んでいれば大阪の税務署になります。
③申告と納税の期限
申告額は1年間(1月1日~12月31日)の間にもらった額を申告します。
たとえば、祖父から300万円、祖母から200万円をもらったとすれば、500万円の申告をします。
期限は、もらった年の翌年2月1日~3月15日までに申告し、この期間内に税金を納めます。
④延納
贈与税は原則として、現金での一括で納めることとなっています。しかし、次の条件をすべて満たせば、税金を分割で納めることができます。これを延納といいます。
(ア)納税額が10万円を超えていること
(イ)一括納税が困難な理由があること
(ウ)担保を提供すること
延納を申請するには、もらった翌年3月15日までに税務署長に「延納申請書」を提出し、許可が下りれば延納ができます。なお、延納は分割で納めるので金利と同様の利子税を納めなければいけません。
生前贈与は、毎年積み重ねることで大きな効果をあげることができます。しかし現金・預金の贈与については、きちんと贈与ができておらず税務署から認められないケースが非常に多くありますので、実行される際には注意が必要です。
2015年の改正で、「相続税は増税、贈与税は減税」となりました。
相続は「贈与税」の特例を上手に活用することが一番の相続税対策です。もっと詳しく知りたい方は…

